 |
 |
 |
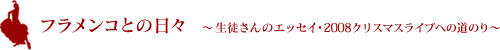 |
 |
 |
 |
 |
 |
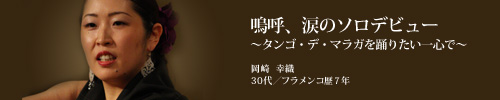 |
 |
 |
 |
フラメンコを始めたばかりの頃、発表会でタンゴ・デ・マラガという曲を観て、「何とかっこいい曲なんだろう。いつか必ず踊りたい!」と思いました。それから数年が経ち、レッスンで習いましたが、発表会で踊る機会はありませんでした。
そのままモヤモヤしていましたが、今回のクリスマスコンサートというチャンスが巡ってきました。
しかし、かつて他の教室でならったタンゴ・デ・マラガを許可していただけるのか、そもそも自分は1人で踊ることができるのだろうかと不安でした。思い切って先生に相談したところ「どうぞやってみてください」との寛大なお返事。許可していただけるとは思っていなかったので、ドキドキして不思議な高揚感のなかで クリスマスコンサートへの道のりがスタートしました。
まだ仕上がっていない踊りをまずは自分なりに仕上げるために練習。そして初めての音合わせ。それはもう、失恋した位ショッキングな結果でした。
今までの発表会では先生がミュージシャンの方に踊りの流れを説明してくださっていたので何も心配いりませんでした。今回は、自分自身で踊りの構成をきちんと説明しなければならないのに初めてで何もできませんでした。さらに生演奏で1人で踊るプレッシャーのため本当に頭の中が真っ白になりました。
ミュージシャンの方や先生に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。もちろん先生からも厳しく指導され、長すぎる曲をもっと短くするようにと言われました。しかし、教わった通りの順番に動くことしかしたことがなく自分で組み立てることは初めてで、音楽的な知識もないため、このコンパス数で曲に合うのか等わからないことだらけでした。
とにかくなんとか強引に縮めて臨んだリハーサル。付け焼き刃の振付けはもうぼろぼろでした。
先生からも「まだ自分でわかっていない感じね。とにかく初めから終わりまで止まらずできるようにしないと」とのお言葉。自分が何もできないことが身に染みてわかりました。踊りに自信がない、足が打てていないからさらにリズムがわからなくなり、パニック状態になってしまう。「もう何と不甲斐無い!」と惨めな気分でした。周りの人はあんなにできるのに、、、と比較して落ち込んだりもしました。「もしかしてできるかもしれないらやってみよう。なんてどうして考えてしまったのだろう???」と情けなくなりました。大好きなタンゴ・デ・マラガの曲をうっとり聞きながら踊りたいなんて、とんでもなくバカなことを考えてしまったと思いました。カンテとギターとの中で、たとえどんなに頼りないバイレでも自分の役割を果たさなければ一曲は成立しないことを改めて痛感しました。
まずは最初のリズムを決める足をきちんと打てるようになろうと考えました。偶然コンパスにはまったことに、当の本人がビックリしてしまうのではなくて、はまって当然になりたいと意識しました。もちろん、頭で数えたものと同じように打つことは難しく、弱々しい音もすぐに直るものではありませんが、最初のリズムが決まれば心も落ち着くので、ここに意識を集中しようと考えたことは私の中では快挙だったと思います。それでも、フラメンコを始めて7年位になるのにこんなにも何もできないということに唖然としました。クラスでみんなで踊る中ではわからなかった自分のできなさ加減がよくわかり、厳しくはありましたが大変勉強になりました。
そして当日。もう不安がっても仕方ありません。最後のデートの気分でスタジオへ。みんなでお化粧したりして少しリラックスできました。とにかく「最初から最後まで踊りきる!」です。お客様も入り、クリスマスコンサート開始です。みんなを応援する気持ちと自分の不安を紛らわす気持ちとでハレオをかけました。そして、そういえば始めたばかりの頃はハレオのかけ方もわからなかったなあ、と思ったら、不思議なことに、これまでお世話になった先生方の言葉を思い出しました。
「自分の踊りの前に、あ〜緊張するな〜、と閉じこもってないで一緒に舞台を盛り上げられるようにね」ということ。また「踊りにはその人が出る」という言葉も思い出しました。今の私の踊りには何が出ているのでしょうか?自分をよくわかっていないことが自信の無さとしてあらわれているのでしょうか?
最初にフラメンコを教わった先生、タンゴ・デ・マラガを教わった先生、そして平先生、これまで3人の先生に教わることができ、とても感謝しています。そしてそれぞれの教えを胸に自分なりに頑張って、今の私の踊りを踊り切ることができますように、と祈るような気持ちでいよいよ本番です。
自信ある顔をしてミュージシャンの方とステージへ進み出ます。ギターが始まり、カンテが入り次は私です。まず最初の足を3つ。 とりあえずいいような気がします。その後は夢中でしたが無事に最後まで踊ることができました。技術的なことや表現力の課題は山積みでも、とにかく最初から最後まで踊ることができて本当にほっとしました。アーティストの優しい音楽とお客様の温かさがとても心に残りました。そして、機会をくださった平先生、低レベルな私を支えてくださったミュージシャンの方達、優しくしてくれたスタジオの仲間、観てくださったお客様、フラメンコに没頭する私を快く(?)見守ってくれた主人、周りの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
先のことはわからないのですが、とにかく今回タンゴ・デ・マラガを踊ることができ、自分自身の心残りが1つ減りました。できないことがよくわかったので今後 の課題として取り組みます。スッキリ失恋して自分磨きに精を出すように地道に頑張ります。つらい事もありましたが、私にとって「嗚呼、涙のソロデビュー」 として、とても有意義なクリスマスコンサートだったと思います。
|
 |
 |
 |
ソロで踊るということは、自分と向き合うということですね。自分が動かなければ始まらないし、始まらなければ終わることもありません。自分に何ができるのかを、思い悩みこの一曲のために努力し、得られた結果は、きっと今後も岡崎さんの記憶に素晴らしい思い出としてよみがえることと思います。
他人の踊りを見て、評価をしたり何かを言うのは簡単です。でも、実際にやり遂げることの大変さとそこから得られる感動は、やった人にしかわからないもの。この挑戦で、岡崎さんは一人の踊り手として格段に進歩したと思います。そして、今回このエッセイを通して、こんなに様々なことを心に思い描いていたのだということを知り、私も感激いたしました。まだまだ本当に課題は山積みですが、本当の意味での輝かしい第一歩を踏み出したという感じですね!今後も頑張ってくださいね! |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2008年の冬、いつかは出演したいと思っていたクリスマスライブに出演することができました。
ただ娘、息子と一緒にセビジャーナスになるとは、思ってもみない展開でした。
6年前の夏、娘がもうすぐ1歳になるという時、その頃住んでいた大井町のカルチャーセンターで託児施設付きフラメンコスクールがあることを調べ、平先生のレッスンを受けました。
私とフラメンコの出会いは卒業旅行で行ったマドリッドにあるタブラオでした。かなり年配のバイラオーラの踊りが素晴らしく、年齢や体格に関係せず、パワフルで心を揺さぶるその踊りを、いつか自分もやってみたいと心に誓ったものでした。
それからかなり時間は空いたのですが、スペインでの熱い思いが体験レッスン初日に思い出され、教室は発表会前の緊張感漂う雰囲気でしたが、私はそんなことお構いなしに一人でバタバタしていただけで十分満足し、その日に入会してしまいました。娘も託児の先生にあっという間に慣れ、その後すぐに同じ年頃の子どものいる方も入り、娘も一緒になってレッスンのある日を楽しみにするようになっていました。託児をお願いしている時間が決まっていることもあって、レッスン後に残って練習が出来ない時は、同じ初心者の友人とレッスン前に自宅で練習をしてから行くということも何度もありました。レッスン前日になると平先生に注意された夢を見てうなされたりもしましたが、とにかく夢中で必死についていこうとしていました。
カラコレスが完成し初舞台!と思ったとき二人目を妊娠したため出演はできませんでした。が、発表会での先生の踊りを初めて見て感動と決意を新たにしました。
二人目を出産してから一ヶ月経った頃、友人に家まで来てもらい進んだところの振りを教わったこともありました。幸いなことに息子はとても丈夫で元気だったので、生後四か月でレッスンを再開した時は、周囲のほうがびっくりしていました。
ようやく初舞台を踏んだのは娘が4歳、息子が11か月の時で、家族にも発表会を見てもらうことができました。娘は初めてフラメンコがどういうものかを理解し たようで、今でも一番やさしい理解者です。息子はお腹の中でずーっと音楽を聞いていたのか、全曲大人しく聞いていたようでした。
その後同じクラスに息子と同じ年のお子さんのいる方が復帰され、息子にも友達が出来、私にとってもさらに心強い友人となりました。カルチャーセンターが閉鎖され神田スタジオに移動すると決まったとき、困ったのが子供の預け先のことでした。母親が安心してお願いできる託児の先生を探すのは簡単なことではありません。子どもたちが慣れ親しんでいる先生に個人的に引き続きお願いすることができ心から安心しました。
そして去年のクリスマスライブで、セビジャーナスを子供と一緒にという話になりました。出演者は私を含めた生徒4人と6歳の娘、3歳の息子、それから小学四年生と5歳の子供たちで踊るというのです。急な話だったので引き受けてみたものの、練習する時間もほとんどなく、子供はコンパスなんて言っても分からないので、時間がある時にひたすら曲を流して曲の雰囲気だけ覚えさせました。振りも娘には簡単に、息子には最初と最後のポーズだけ教えました。しかし母の不安を余所に子供たちは衣装を着た途端その気になり、ポーズをしっかり決め、結局子供たちにすべてお客様の視線は持っていかれました。こんなことができるのもフラメンコのよさなのかと思った瞬間でした。
子供が小さいうちは週に1時間のレッスンだけしか自分の時間は作れないので、上達するのも曲を覚えるのも時間はかかりますが、その時間の充実した気持ちは初めて体験に行った時と今もほとんど変わっていないような気がします。子供がいたからここまで打ち込めたのかもと思う時もあります。今後も先生方に感謝して日々レッスンに励んでいきたいです。
|
 |
 |
 |
託児制度のあるカルチャークラスを引受けた時は、若いお母様たちがお子さんを預けてまでレッスンをするということをあまり深く理解していませんでした。途中、私自身も出産を経験し、レッスンに参加されているお母さま方がどんなお気持ちでそれまで続けてこられたのかということを私なりに思うようになり、自分が講師としてできる限りのことをとにかく精一杯やるという覚悟を新たにしました。昼時間帯のお母様のクラスといえ、厳しくレッスン内容を展開してまいりました。縣さんは、当初からとてもがんばっておられ、華奢な体格からは想像もつかないほどのバイタリティーで、二人のお子さんとベビーカーを抱えて奮闘し、前の週にやったことを翌週確実にしてくるなど驚くべき集中力を発揮していました。
この頑張りを何とか形にしたいという思いで今日まで応援し続けました。丁度、クリスマスライブをひとつの区切りと思い、このクラスの仲間でできることをやってみてはと思い、お子さんとのジョイント出演を提案してみました。結果、温かみのある踊り本来の楽しさというものが見ていて伝わりとてもよい思い出となりました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 「生徒さんのエッセイ・バックナンバー」へ戻る 「生徒さんのエッセイ・バックナンバー」へ戻る |
 |







